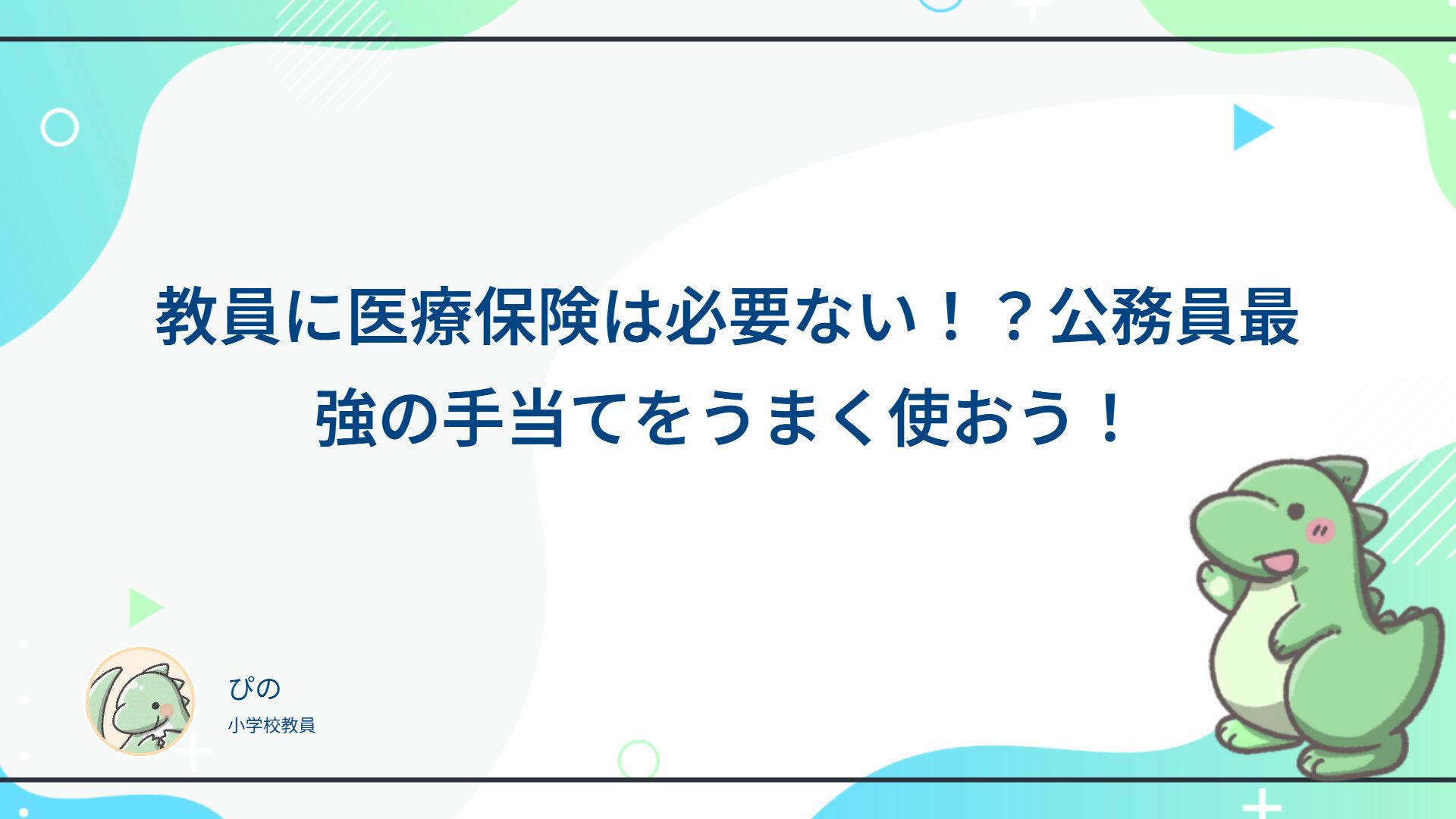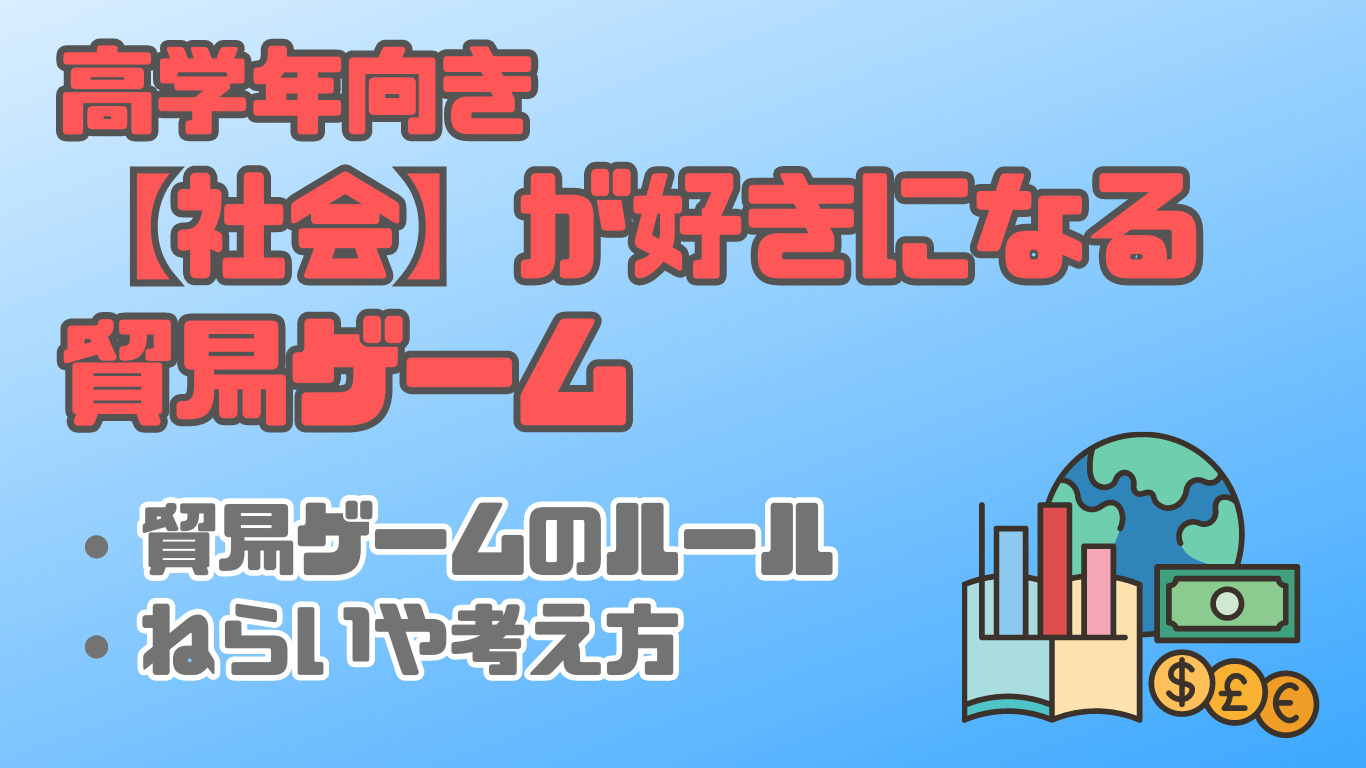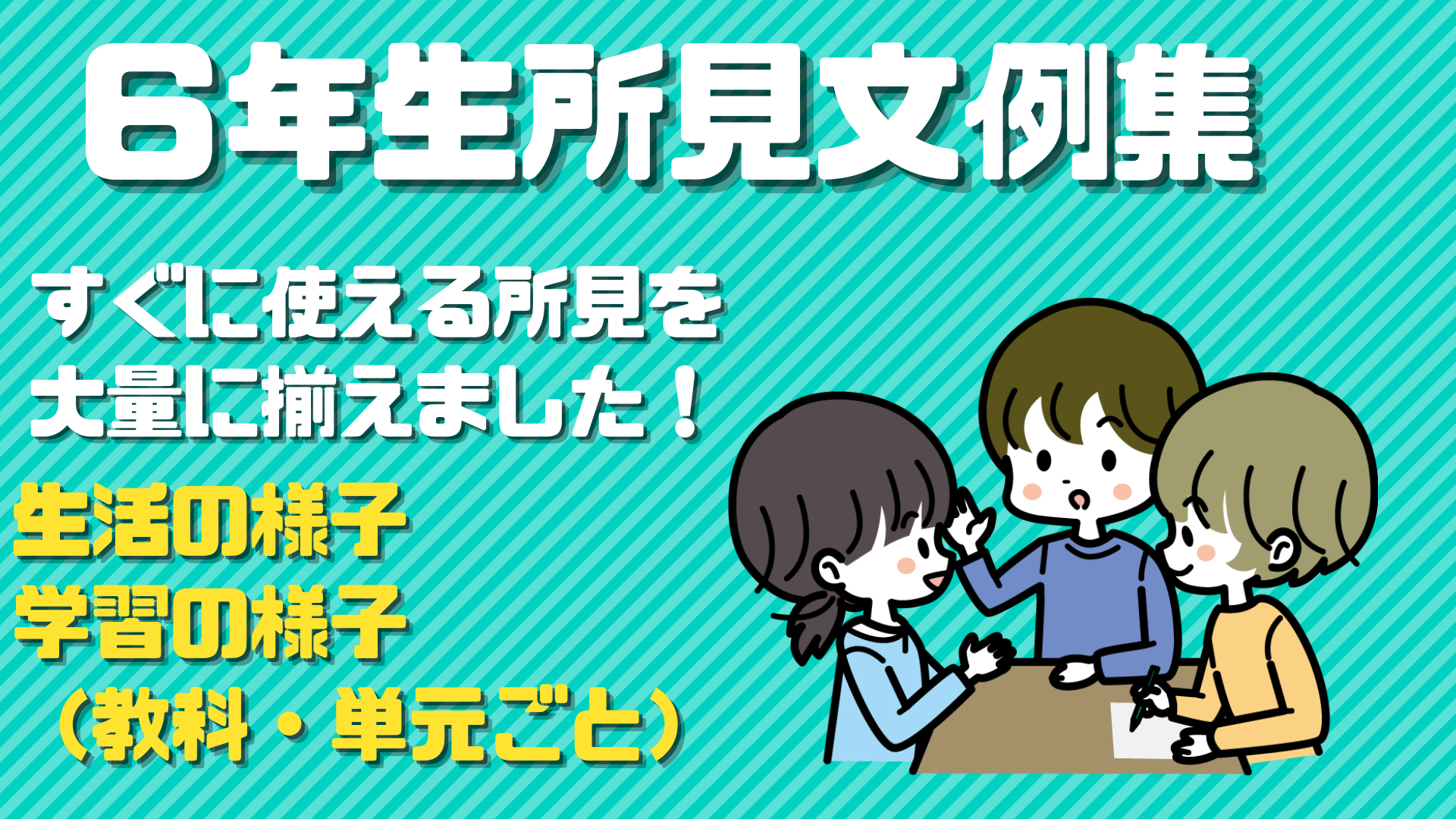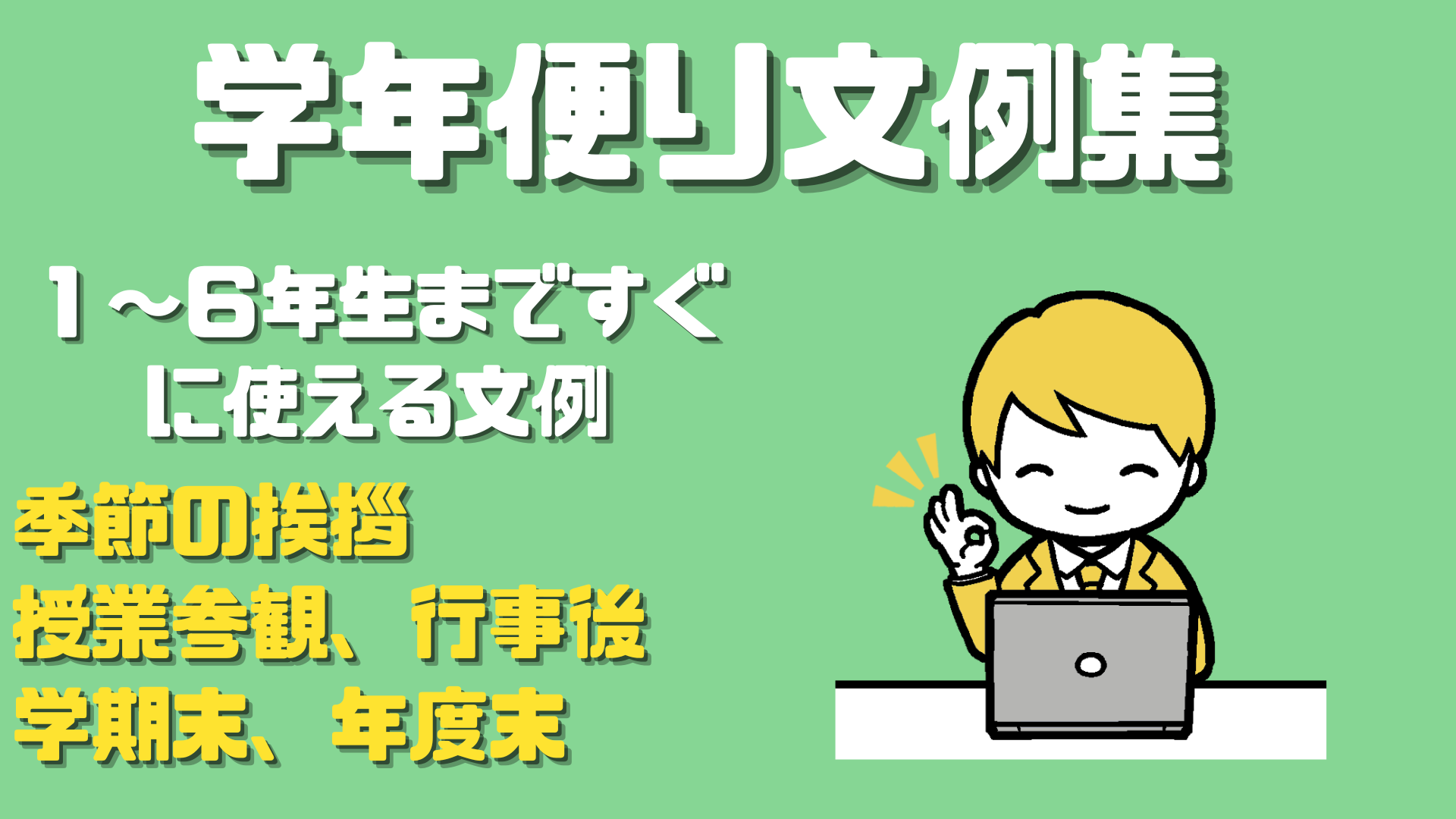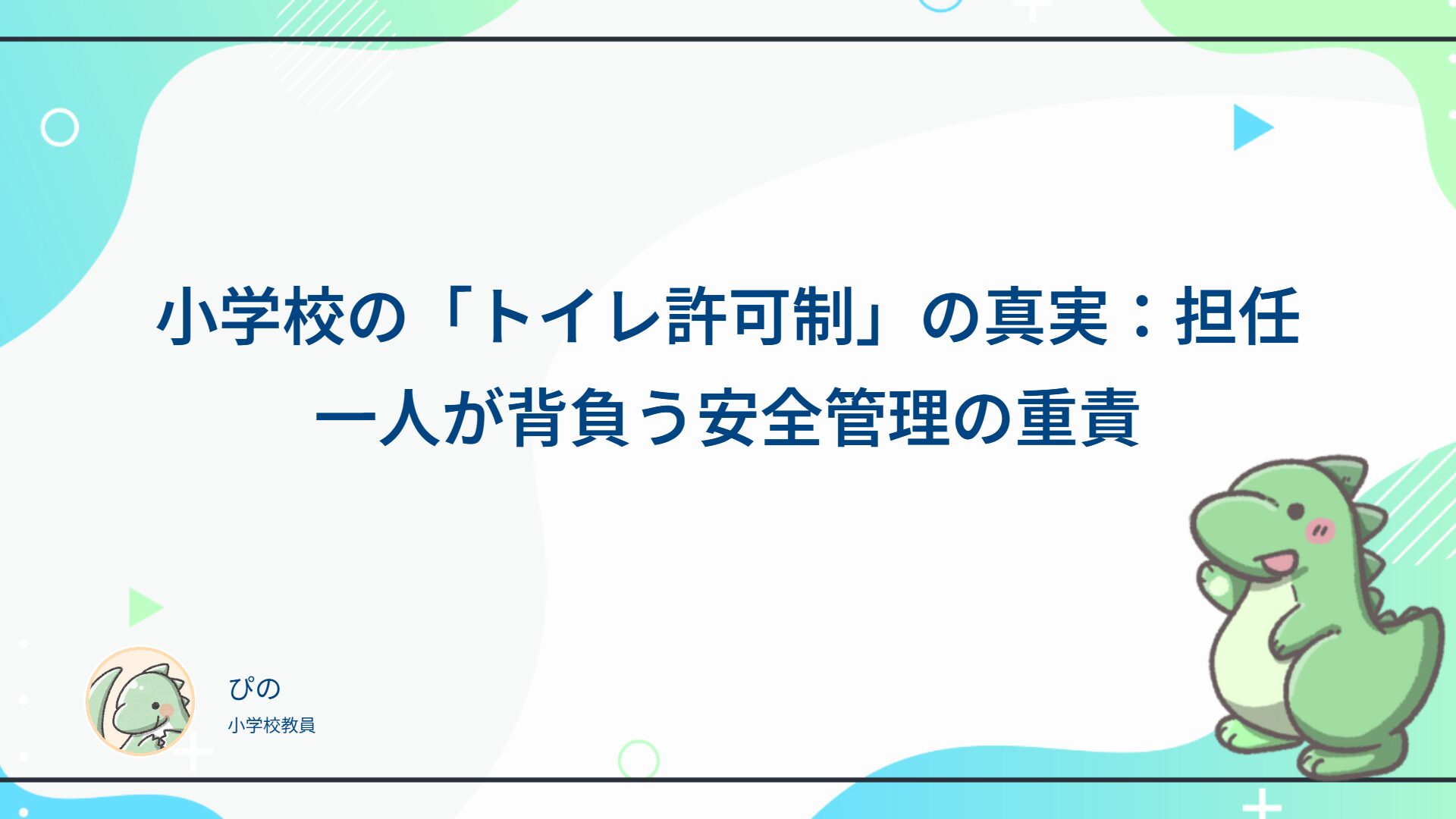【小学校教員向け】指示待ち児童を減らす!時間意識を育てる学級経営の秘訣

教室で「先生、次は何をすればいいですか?」「これでいいですか?」という声をよく耳にしませんか?
子どもたちが常に指示を待っている状態は、自立した学習者を育てるという教育の本質から外れています。
教員の言葉でしか動けない児童を作るのではなく、子ども自身が判断し行動できるようになることこそが、教育の本質です。
そのために最も有効な手段の一つが「時間」を意識させる指導です。
「好かれる教員」と「育てる教員」の違い
子どもに好かれる教員が良い教員とは限りません。
表面的な関係性だけでは、子どもは教員の指示を待つばかりで、自立した行動力を養うことはできません。
子どもが真に育つとは、担任(大人)がいなくても自分で考え、行動できる力を身につけることです。
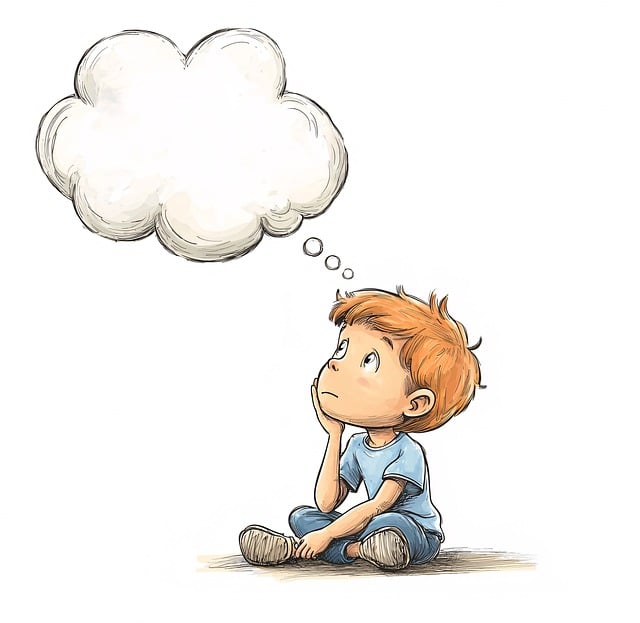
担任の話だけを聞くクラス、いわゆる「学級王国」をつくることが学級経営だと考える教員は少なくありません。
「先生が言ったから」ではなく、「今この時間だから自分がすべきことはこれだ」と判断できる子どもを育てることが、真の学級経営の目標と言えるでしょう。
なぜ「時間」が効果的なのか
担任がいなくても動ける児童を育てる上で、「時間」は非常に有効なツールとなります。その理由を詳しく見ていきましょう。
担任の指示に頼らない自律性を育む
時間割や時計を見ることで、子どもたちは「いつまでに何をすべきか」を自分で判断し、行動できるようになります。
授業の準備、片付け、休憩時間のけじめなど、具体的な行動が時間の意識によって促されます。
教員が逐一指示しなくても、子どもたちは時間という共通のルールに従って動くことができるため、指示待ちの姿勢から自然と脱却していきます。
時間はどこでも共通の普遍的な指標

時間は場所や状況を選ばず、常に一定の流れで進みます。
そのため、移動教室や学校行事等、普段と異なる環境下でも、時間を意識することで子どもたちは混乱することなく行動できるようになります。
時間の指導が行き届いていると、普段の学校生活はもちろんのこと、校外学習や修学旅行等の宿泊を伴う学習活動でも発揮されます。
担任が大きな声を出して指示を出さなくても子どもたち自身の判断で動き始め、時間になれば静かに指示を待つことができるようになります。
新担任も助かる!「時間」を守る子どもたちのスムーズなスタート
学級経営は担任の個性が強く表れるものですが、時間の感覚はどの学年、どの教員の下でも共通しています。
時間を守るという基本的なルールを身につけた子どもたちは、クラス替えがあっても新しい環境でスムーズに学校生活を送ることができ、次の担任の負担軽減にも繋がります。
そして何より、この時間管理能力は進学や社会に出た後も、一生役立つ財産となります。
時間通りに行動できる学年は、普段の授業の質も高くなっていきますね。(研究授業ではないことが重要)

学習者主体の学習にも必要不可欠

個別最適な学びを実現するためにも時間の指導は欠かせません。
学習者主体の学習には「学習課題」や「学習計画」「時間」などの共通事項をしっかりと抑えることで、担任の指示の時間を極力減らし、その分を学習活動に充てることができます。
「時間」の指示に従って動くことができるようになれば、担任も配慮が必要な児童に時間を掛けて指導をすることが可能になります。
時間を意識させるための具体的な方法
教室環境の工夫
時間を意識させるために有効なのは何より時計です。
しかも、アナログ時計だけでなく、デジタル時計も教室に設置することで時間への意識をより高めることができます。
アナログ時計は時間を感覚的に把握するために活用できますが、分単位でみると曖昧なことが多く、「1分くらい遅れても」という感覚が生まれることで、全員の行動が揃いづらいデメリットがあります。
デジタル時計は、時間の経過を明確に捉えやすく、1分(1秒)単位での子供達の行動を促すことができます。
また、タイマー機能付きのデジタル時計を活用し、学習活動の時間配分を視覚的に把握させることも効果的です。
一番のオススメは、「SUZUKIスクールタイマー」です!

- 画面が大きく、教室の後方からでも見やすい
- アラーム、タイマー、時計等機能が充実している
- マグネット(強力)が付いており、黒板に貼り付けやすい
- 操作がとてもシンプルで分かりやすい(ボタンが少なく、説明書いらず!)
- 薄型で使用感が良い
- 電池駆動(充電や給電がいらないのはとても助かりました)
- 値段が高い(型落ちになると、多少価格は下がりますが・・・)
- 落とすと液晶が割れやすい
とても便利で使いやすいのですが、液晶が割れやすいのが一番の難点だと感じます。マグネットが強力であるがゆえに外すときに力が必要で、外したときに勢い余って床に落としてしまいがちです。(薄型なのがまた落としやすい。。。)
私も買ってすぐに液晶を割ってしまい購入し直しています・・・

製品自体はとても良いのですが、取り扱いには十分に注意する必要があります。マグネットよりも、壁に掛けて利用したほうが壊れづらいかもしれません。
そして次におすすめなのが、

- 価格がリーズナブル
- 大きくて時間が見えやすい
- アラーム、タイマー、時計等機能が充実している
- リモコン操作が可能なため、高い所に掲示できる
- リモコンの操作範囲が狭い(感度があまりよくない)
- 給電タイプ(コンセントが必要)
- なんとなくうさんくさい(これは完全に主観ですが・・)
最初は購入するのに躊躇しましたが、購入して4年が経った現在でも、特別問題なく利用できています。
特に高所に掲示して、リモコンで操作できるのはスクールタイマーと差別化できる点です。
直接触らずに操作できるのは、長期的にみるととても助かりました。
商品ページはなんとなく胡散臭さを感じるのですが、価格も高くないので試す価値はあります!
教員自身の時間管理
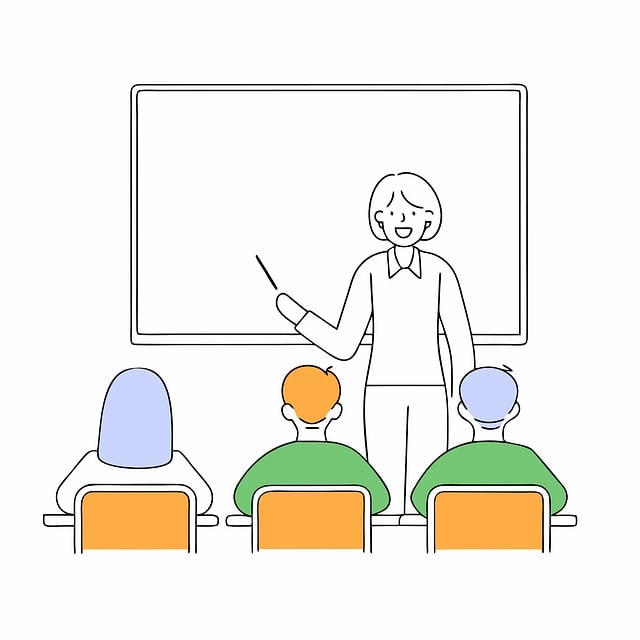
教員自身が時間を意識し、授業を時間内に終える努力をすることが何よりも大切です。
子どもたちは教員の姿から多くを学びます。もし授業が長引いてしまった場合は、その分を休憩時間に充てるなど、子どもたちの時間を尊重する姿勢を示すことが信頼関係に繋がります。(前述タイマー活用)
「時間は有限であり、教員も子どもも互いの時間を大切にする」という共通認識を持つことで、クラス全体の時間に対する意識が高まります。
また、担任の話を短く終わらせることも大切です。だらだらと同じ話を繰り返すのは時間を無駄にするだけでなく、担任の話を聞かなくなってしまいます。
端的な指示は子供にメリハリをつけ、時間を有意義に利用することに繋がります。

指導の際の留意点
バランスを意識する

時間を意識させることと、焦らせることは別です。特に低学年では、過度なプレッシャーにならないよう配慮が必要です。
「早く、早く」と急かすのではなく、「自分のペースで、でも時間を意識して」という姿勢で指導しましょう。
また、個人差を考慮し、一人ひとりの能力や特性に応じた支援を心がけることも大切です。
時間厳守と同時に、丁寧さや正確さも大切にすることを教え、質と速さのバランスを意識させましょう。
成長を認め、励ます
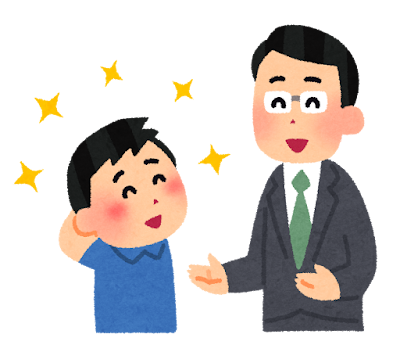
時間を守れるようになった姿を具体的に褒めることで、子どもたちの自信につながります。
「今日は全員が時間通りに集合できましたね」
「昨日より5分早く準備ができたね」
など、成長を具体的に示すことが効果的です。
時間管理ができた日とできなかった日を比較し、「時間を守ると後の活動に余裕が生まれる」ことを実感させることで、子どもたち自身が時間管理の大切さを理解できるようになるでしょう。
まとめ
時間を意識させる指導は、単に時間を守らせるだけが目的ではありません。
日々の教育活動の中に「時間」という視点を意識的に取り入れることで、子どもたちの自立した成長をサポートすることができます。
子どもが「先生の指示」ではなく「時間」を意識して動けるようになれば、教室は自然と活気づき、教員の負担も軽減されます。
子どもたち自身が「自分で考えて行動できる」という自信を持つことにもつながります。
この自信と時間管理能力は、学校生活だけでなく、将来社会に出たときにも大きな財産となることでしょう。