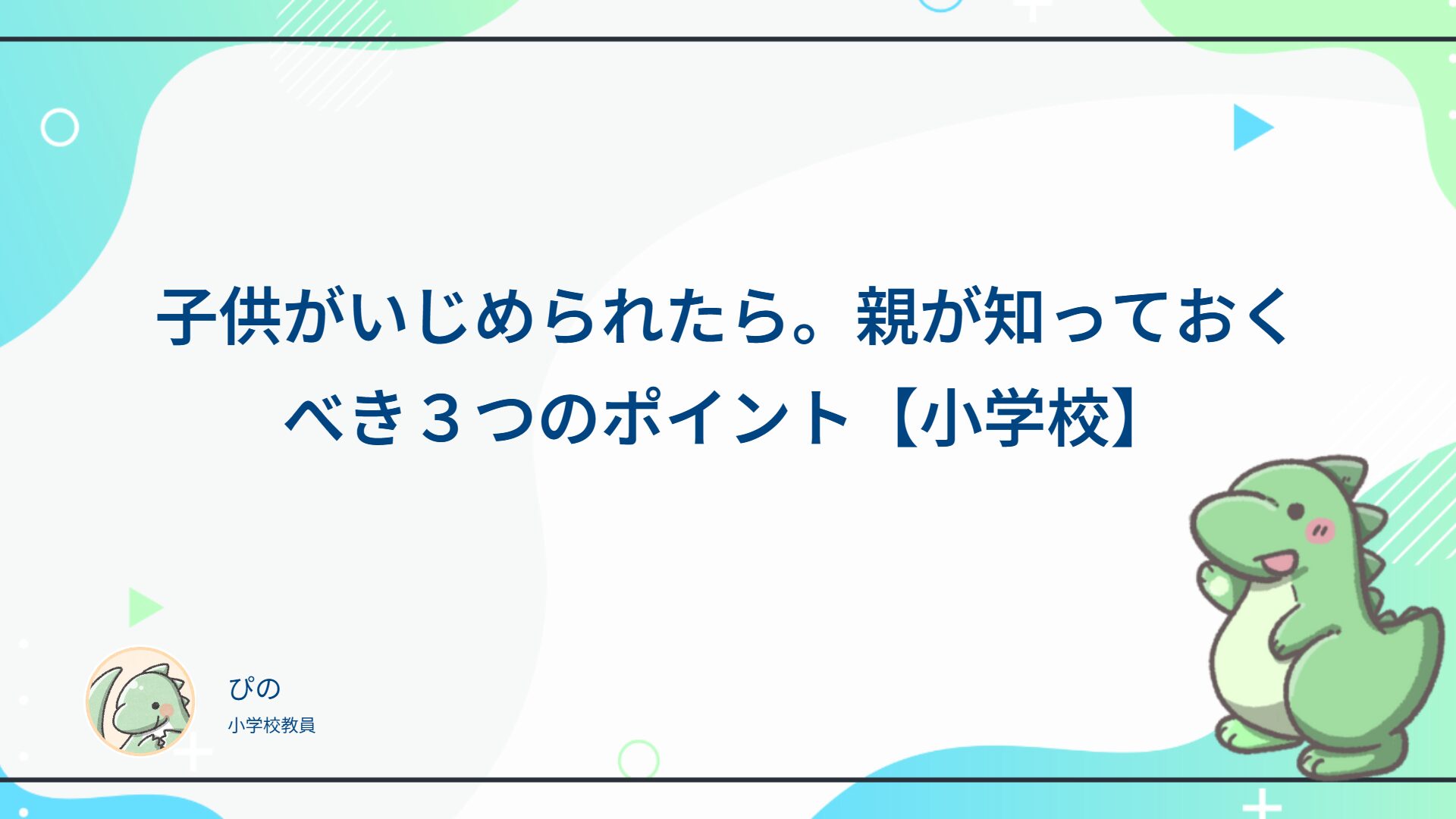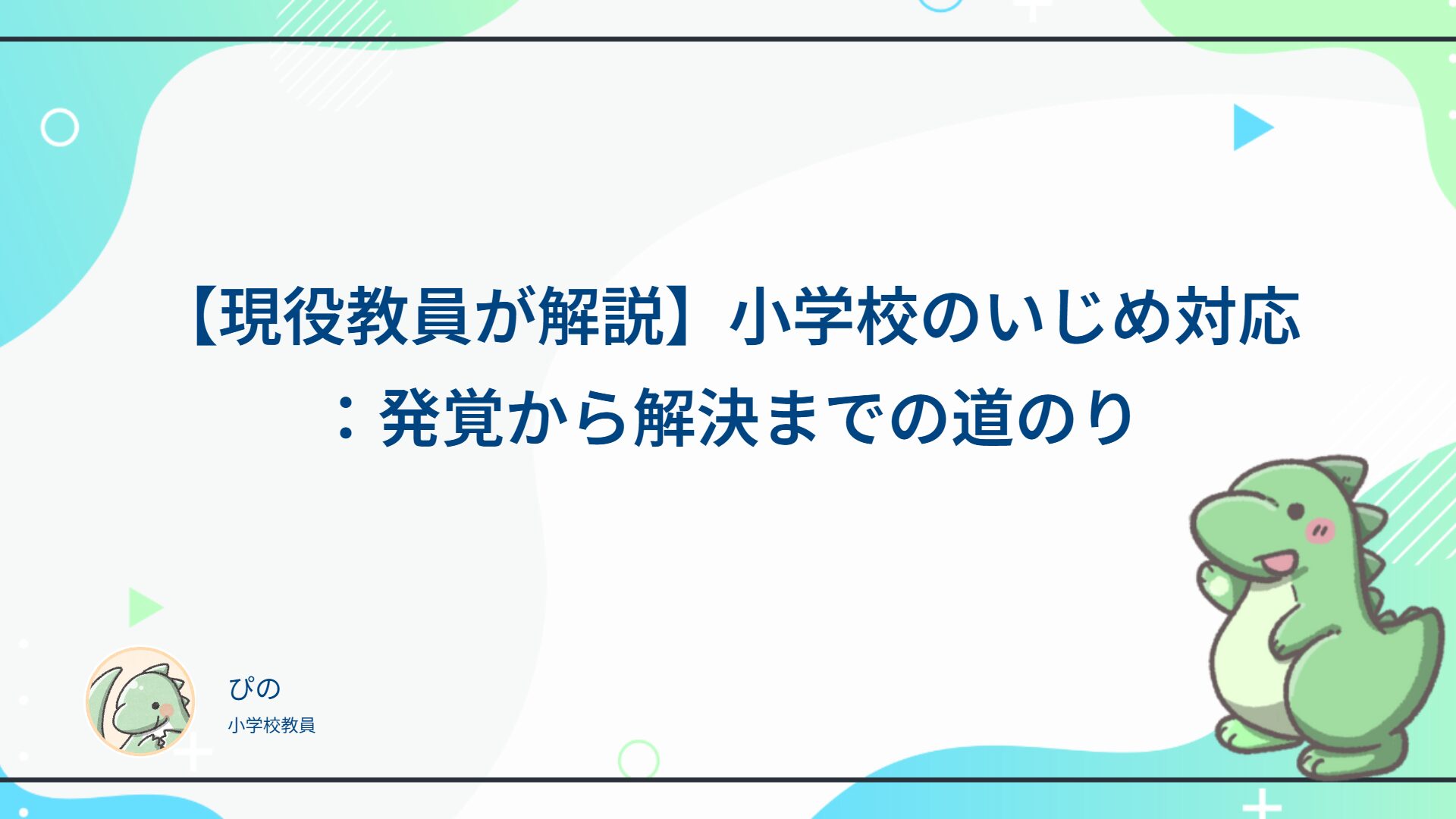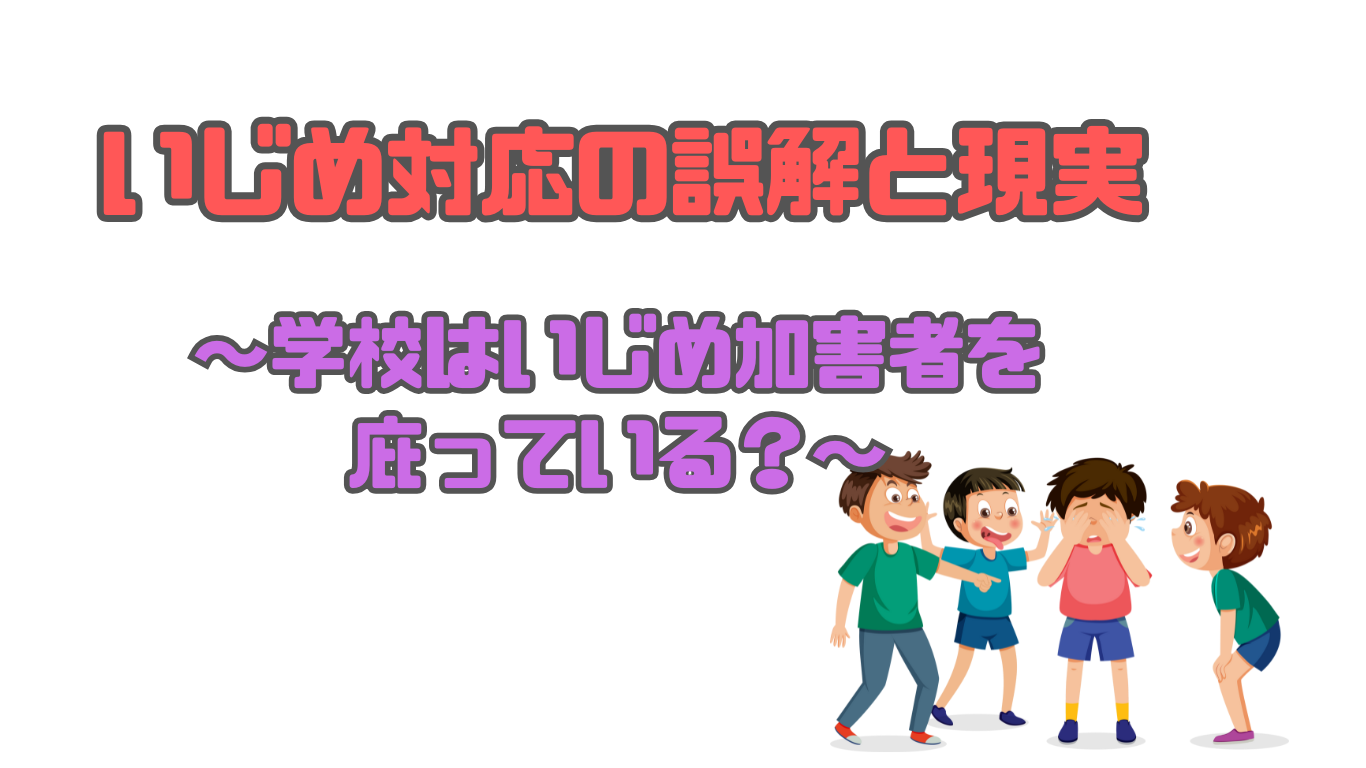【学校からいじめの連絡】親が学校に聞くべき質問と心構え
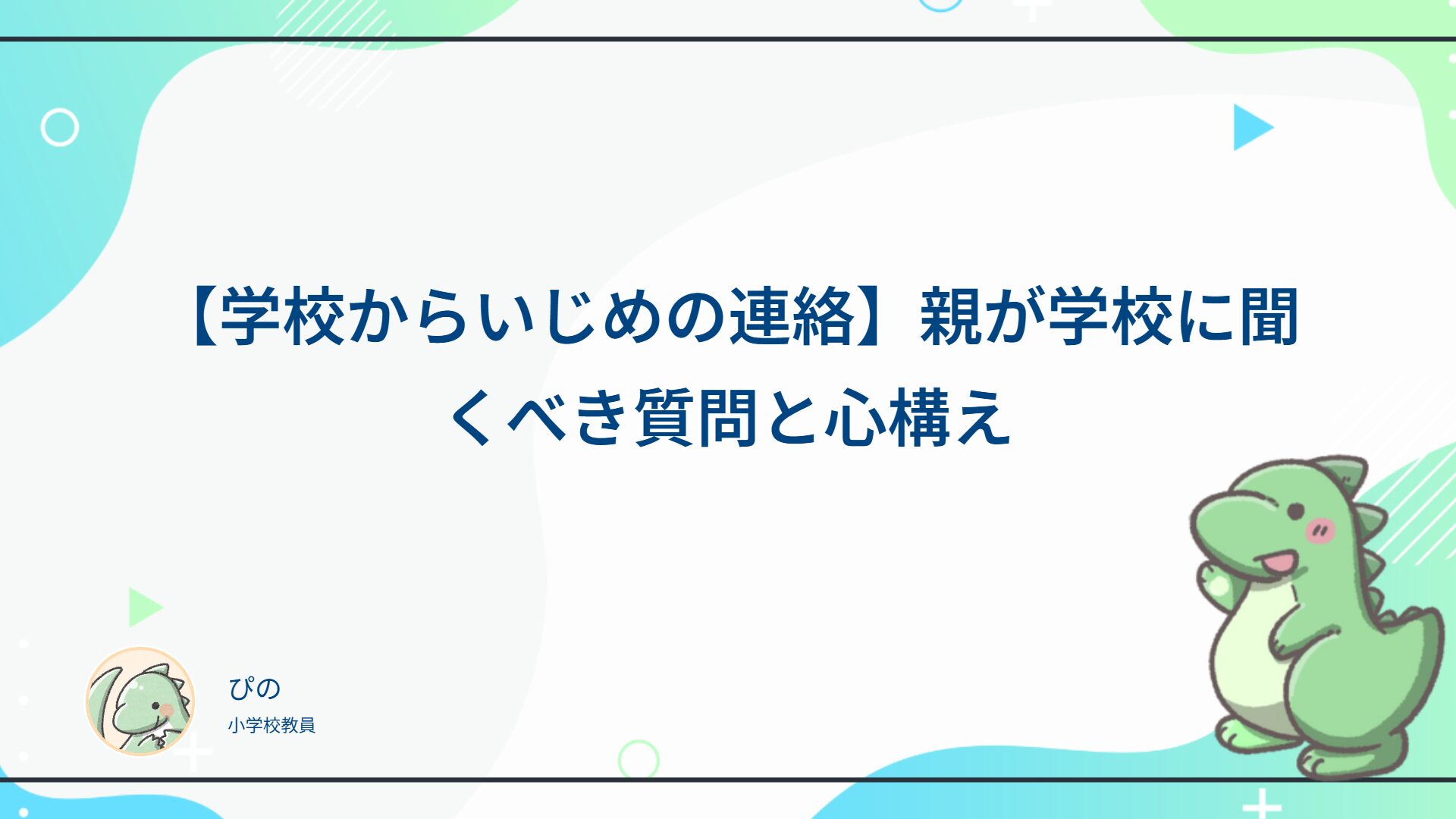
ーー「お子さんがいじめられています」——
学校からこのような連絡を受けたとき、多くの保護者は不安や怒り、時には自責の念に駆られるものです。子どもの苦しみを知ったとき、冷静さを保つのは簡単ではありません。
しかし、この難しい状況の中で最も大切なのは、感情的にならずに建設的な解決策を見つけることです。そのための鍵となるのが、学校に対して効果的な質問をすることです。
この記事では、いじめの連絡を受けた際に学校に聞くべきことを具体的にお伝えします。適切な質問は、学校との協力関係を築き、お子さんを守るための強力な味方になります。
なぜ「効果的な質問」が、問題解決と子供の成長に繋がるのか
1.1 学校は万能ではないという認識を持つ

まず理解しておきたいのは、「学校も完璧ではない」ということです。
教員の中には新卒の先生や、転職してきたばかりの先生、あるいはいじめ対応の経験が少ない先生もいます。
また、教員一人あたりの担当生徒数が多く、全ての子どもの様子を常に把握するのは物理的に難しい現実もあります。
いじめ問題は複雑で、表面化しにくい特徴があります。
休み時間や放課後、トイレなど教員の目が届きにくい場所で起こることも多いのです。
「なぜ先生は気づかなかったのか」と思うのは自然なことですが、学校だけで完璧な対応を期待するのではなく、一緒に問題を解決する姿勢が大切です。
1.2 責めるのではなく「協力」という視点
学校の対応に不満を感じるのは当然かもしれません。
しかし、学校を責めることが問題解決につながるでしょうか?
保護者の目的は「学校を責めること」ではなく、「子どもが安心して学校生活を送れるようにすること」のはずです。
そのためには、学校との協力関係を築くことが最も効果的です。
実際の会話例:
非協力的な例: 「なんでこんなことが起きるまで気づかなかったんですか!学校の管理責任はどうなっているんですか!」
協力的な例: 「この状況を改善するために、私たち親としてどのように協力できるでしょうか。一緒に子どもを守っていきたいと思っています。」
1.3 足りない部分を補い合うという姿勢

学校だけでなく、親も完璧ではありません。
思い返せば、学校から子どもの様子を教えてもらったり、アドバイスをもらったりして助けられたことがあるのではないでしょうか。
お互いの足りない部分を補い合い、子どものために協力することが重要です。
いじめの問題は、親と学校が一丸となって取り組むべき課題なのです。
事実確認のための「聞くべきこと」
いつ、どこで、誰が、何をしたのか?
まずは基本的な事実を確認します。具体的に次のような質問をしましょう:
- 「いつ頃から、このようないじめが発生していたのでしょうか?」
- 「どこで起きていたのですか?教室内、廊下、校庭、その他の場所ですか?」
- 「関わっている児童は何人くらいで、どのようなことがあったのですか?」
- 「具体的にどのような行為(言葉によるもの、叩くなどの身体的なもの、仲間外しなど)があったのでしょうか?」
子供は話す相手によって話の内容が変わることが多くあります。
親にに話してくれたことが必ずしも事実ではないことを頭に入れ、学校ではどのように話していたのかを確認する必要があります。
家で話すことと、学校で話したことの共通点や相違点を確認しましょう。
話が食い違う点がある場合、そこを確認する必要があります。

どのような状況で発生したのか?
いじめの背景を理解するために、次のような質問も有効です
- 「きっかけとなった出来事はありましたか?」
- 「いじめが起きたとき、周りに他の児童はいましたか?その児童たちはどのような反応をしていましたか?」
- 「先生は近くにいましたか?いた場合、どう対応しましたか?」
これらの質問を通じて、いじめの発生状況や背景をより詳しく知ることができます。
これまでにも同様の事例はなかったのか?
過去の状況も把握しておくことが重要です
- 「以前にも同じような問題はありましたか?」
- 「もしあった場合、その時はどのように対応されましたか?」
- 「その対応の結果はどうだったのでしょうか?」
過去の事例を知ることで、今回の問題の深刻さや継続性を理解できます。また、過去に効果的だった対応方法があれば、それを参考にすることもできるでしょう。
前担任に話を通してもらうことで、問題点が明らかになることもあります。
学校の対応方針を確認するための「聞くべきこと」
学校は今後どのように対応するのか?
対応の方針について確認し、認識のずれが無いようにしましょう。
- 「これからどのように聞き取りをされる予定ですか?」
- 誰が聞き取りをするのか?担任だけなのか、複数人なのか?
- 聞き取りは休み時間に行われるのか、授業時間にもやるのか?
- 誰に話を聞くのか?加害者だけでなく、目撃者にも聞くのか?
調査の具体的な計画を知ることで、学校が問題にどれだけ真剣に取り組んでいるかがわかります。
また、原則として教員が複数名で個別に聞き取りを行うことが、より客観的で丁寧な対応につながるとされています。

- 客観性の向上
- 複数人で状況を把握することで、担任の一方的な見方や思い込みを防ぎ、より客観的な事実確認が期待できる
- 子供への配慮
- 1人の教員による高圧的な聞き取りを避け、子供が安心して話せる環境を整えやすくなる
- 記録の正確性
- 複数名で情報を共有・記録することで、聞き取り内容の間違いを防ぎ、正確な記録を残すことができる
しかしながら、現実には、時間の制約や担任のいじめに対する認識の違いなどから、必ずしもこの原則が守られないケースも残念ながら存在します。
担任の先生が一人で対応しようとしたり、状況によっては十分な時間をかけずに聞き取りを終えてしまうこともあるかもしれません。
そのような状況に対し、保護者としてできることがあります。
それは、事前に学校へ電話連絡をする際に、「聞き取りは何名の教員で行っていただけるのでしょうか?」といった質問をさりげなく行うことです。

この質問をすることで、保護者側が複数名での聞き取りを望んでいることを学校側に伝える牽制となり、結果として学校側が複数名での対応を検討するきっかけになる可能性があります。
もちろん、学校側の状況によっては、必ずしも複数名での対応が難しい場合もあるかもしれません。
しかし、事前に確認することで、学校側の対応状況を把握し、もし一人での聞き取りになりそうな場合には、その理由を確認したり、複数名での対応をお願いしたりする交渉の余地が生まれます。
3.3 被害者への支援体制について

お子さんへのケアについて確認しましょう
- 「明日以降、子どもが安心して学校に通えるよう、どのような配慮をしていただけますか?」
- 「スクールカウンセラーなど、専門家のサポートは受けられますか?」
- 「席替え等配慮していただくことは可能ですか?」
お子さんの心のケアや安全確保は最優先事項です。具体的な支援内容を確認しておきましょう。
3.4 加害者への指導方針について

加害児童への対応も重要です
- 「加害児童にはどのような指導をされる予定ですか?」
- 「その保護者への連絡はされますか?」
- 「再発防止のために、どのような取り組みをされますか?」
いじめの再発を防ぐためには、加害児童への適切な指導が欠かせません。
しかし、自分が想定している指導と担任が予定している指導が異なる可能性があります。
基本的に指導の方向性は担任から伝えることになっていますが、伝えられなかった場合は確認しておきましょう。
特に、相手の保護者に連絡してほしくない場合は事前に伝えておきましょう。自治体によっていじめ対応のガイドラインは変わりますが、相手の保護者にも連絡するのが通例です。
どのように連絡するのか心配する場合は事前に確認しておくことをオススメします。

保護者への情報共有の方法について

今後の連絡体制を確認しておきましょう:
- 「状況に変化があった場合は、連絡帳(電話)で連絡をいただけますか?」
- 「仕事の都合で、16:00以降に電話をしていただくことは可能ですか?」
継続的な情報共有の体制を整えることで、お子さんの状況変化にも迅速に対応できます。
自分の都合を先に伝えておくことで、円滑に連絡を取ることができます。
質問する際の心構えと注意点
感情的にならず、冷静に話す
子どものことで感情的になるのは自然なことですが、冷静な対話が解決への近道です。深呼吸をして、話す内容を整理してから面談に臨みましょう。
敬意を持って、協力的な態度で臨む
教員も日々多くの児童と向き合い、ベストを尽くしています。敬意を持ち、協力的な態度で接することで、より良い関係を築けます。
メモを取りながら話を聞く
重要な情報は必ずメモしましょう。後で確認したり、経過を追ったりするのに役立ちます。「メモを取ってもよろしいですか?」と一言断っておくとよいでしょう。
不明な点は遠慮せずに質問する
わからないことがあれば、その場で質問しましょう。「これはどういう意味ですか?」「もう少し詳しく教えていただけますか?」と尋ねることで、認識のずれを防げます。
学校側の状況や立場も理解しようと努める
学校にも様々な制約や難しさがあります。一方的な要求ではなく、学校の立場も理解しようとする姿勢が大切です。
完璧な親はいない。お互いを尊重し、支え合う視点を持つ
親も教員も完璧ではありません。お互いの強みを活かし、弱みを補い合うことで、より良い解決策を見つけられます。
まとめ
いじめの問題は、決して保護者だけで、あるいは学校だけで解決できるものではありません。適切な質問を通じて学校と協力関係を築き、子どもを守る体制を整えることが大切です。
学校が万能ではないことを理解し、責めるのではなく協力する姿勢を持つことで、より建設的な解決につながります。
事実確認、学校の対応方針、そして連携のための「聞くべきこと」を意識して、子どもの安全と成長を支えましょう。
何より大切なのは、子どもに「あなたのことを守ってくれる大人がいる」という安心感を与えることです。
親と学校が手を取り合うことで、子どもは再び安心して学校生活を送れるようになるでしょう。
相談窓口情報
いじめ問題で悩んだときは、学校だけでなく外部の相談窓口も活用しましょう。
- 24時間子供SOSダイヤル: 0120-0-78310(全国共通・通話料無料) 子どもたちが全国どこからでも、いじめ等の悩みを24時間いつでも相談できる窓口です。
- 子どもの人権110番(法務省): 0120-007-110(全国共通・通話料無料) 平日8:30〜17:15に、いじめや体罰など子どもの人権問題に関する相談ができます。
- 各都道府県・市区町村の教育委員会: 地域によって連絡先が異なります。 お住まいの自治体のホームページで確認してください。
一人で抱え込まず、様々な支援を活用しながら、お子さんと一緒にこの困難を乗り越えていきましょう。