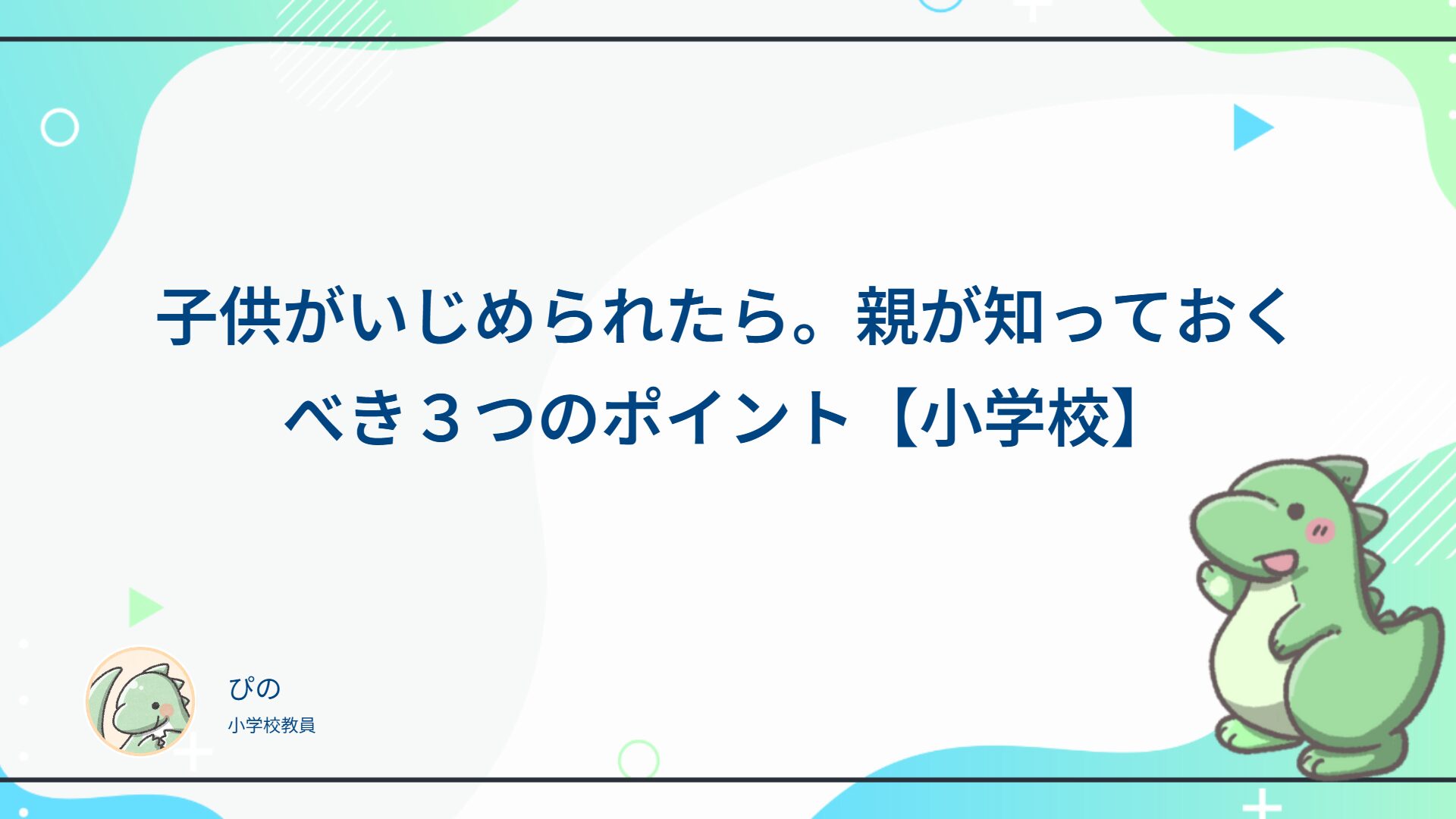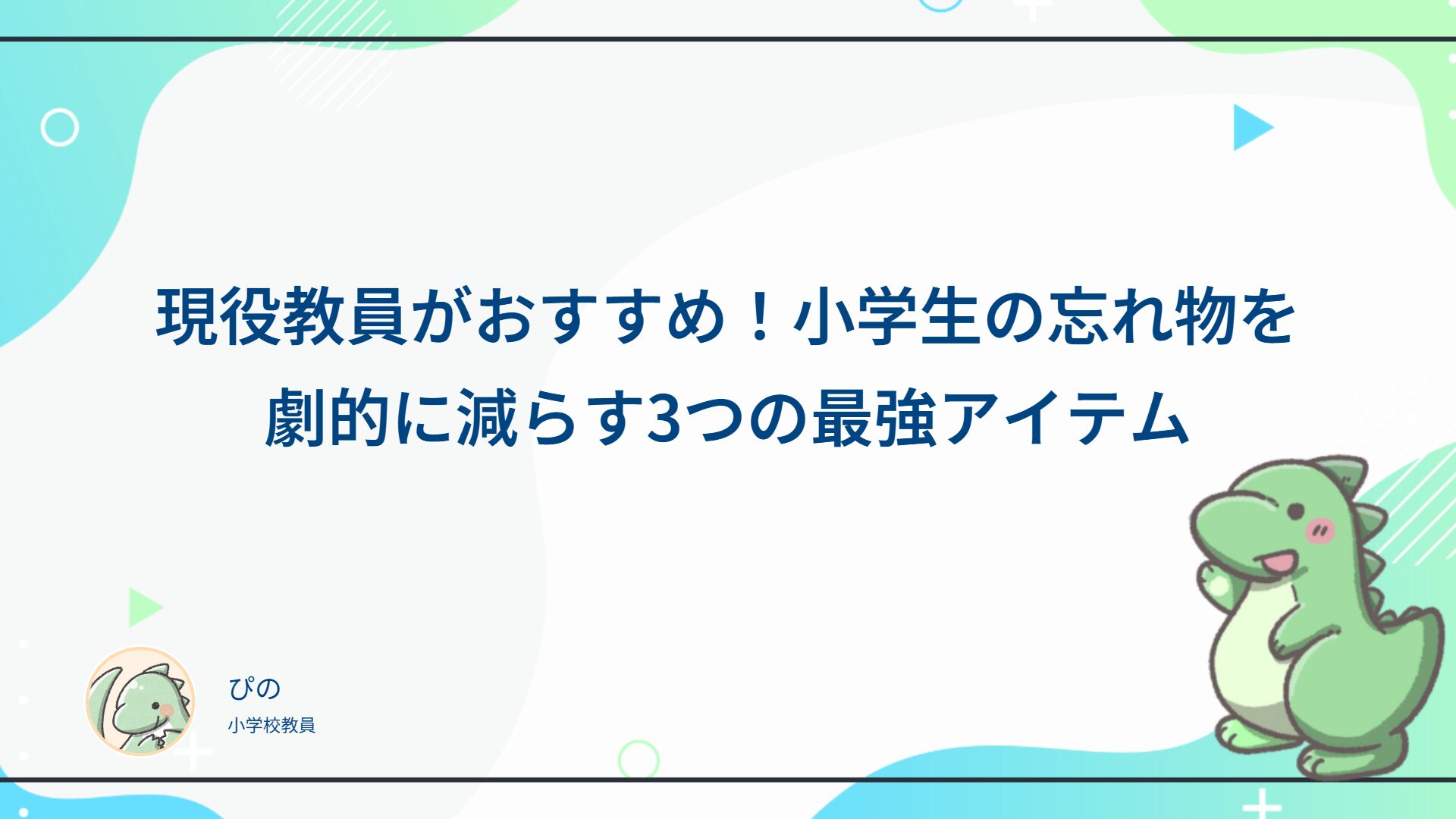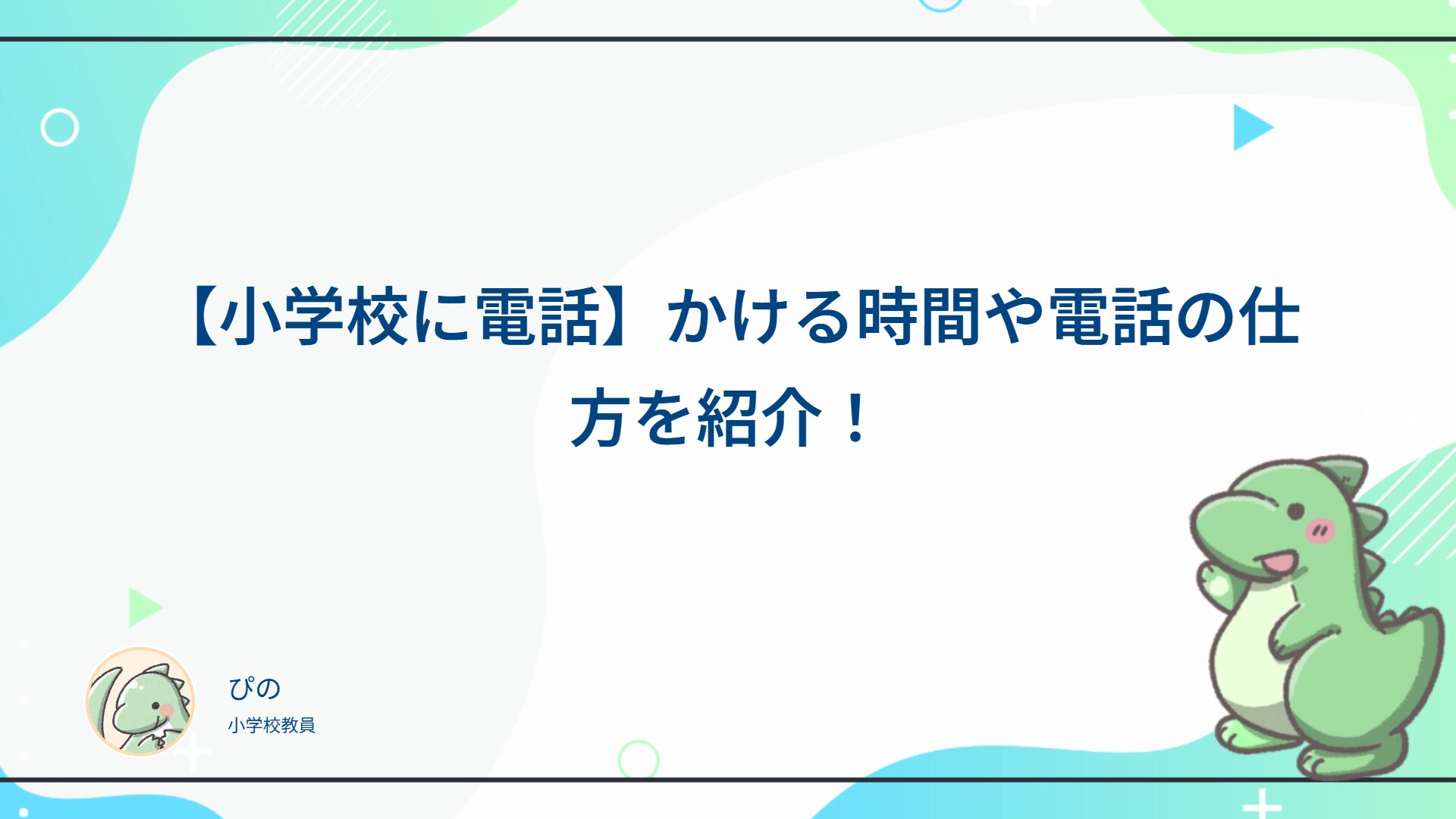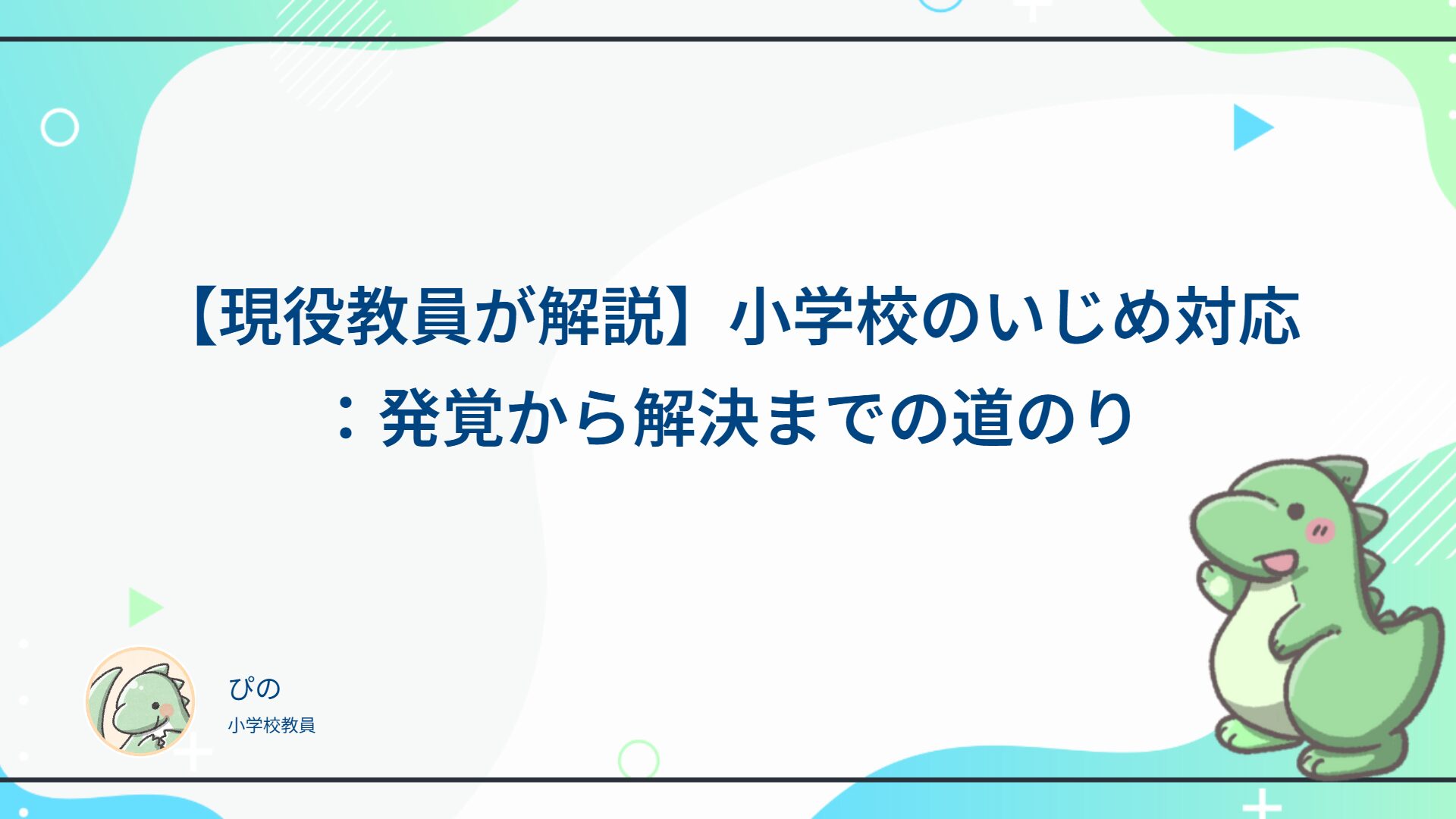小学校の「トイレ許可制」の真実:担任一人が背負う安全管理の重責
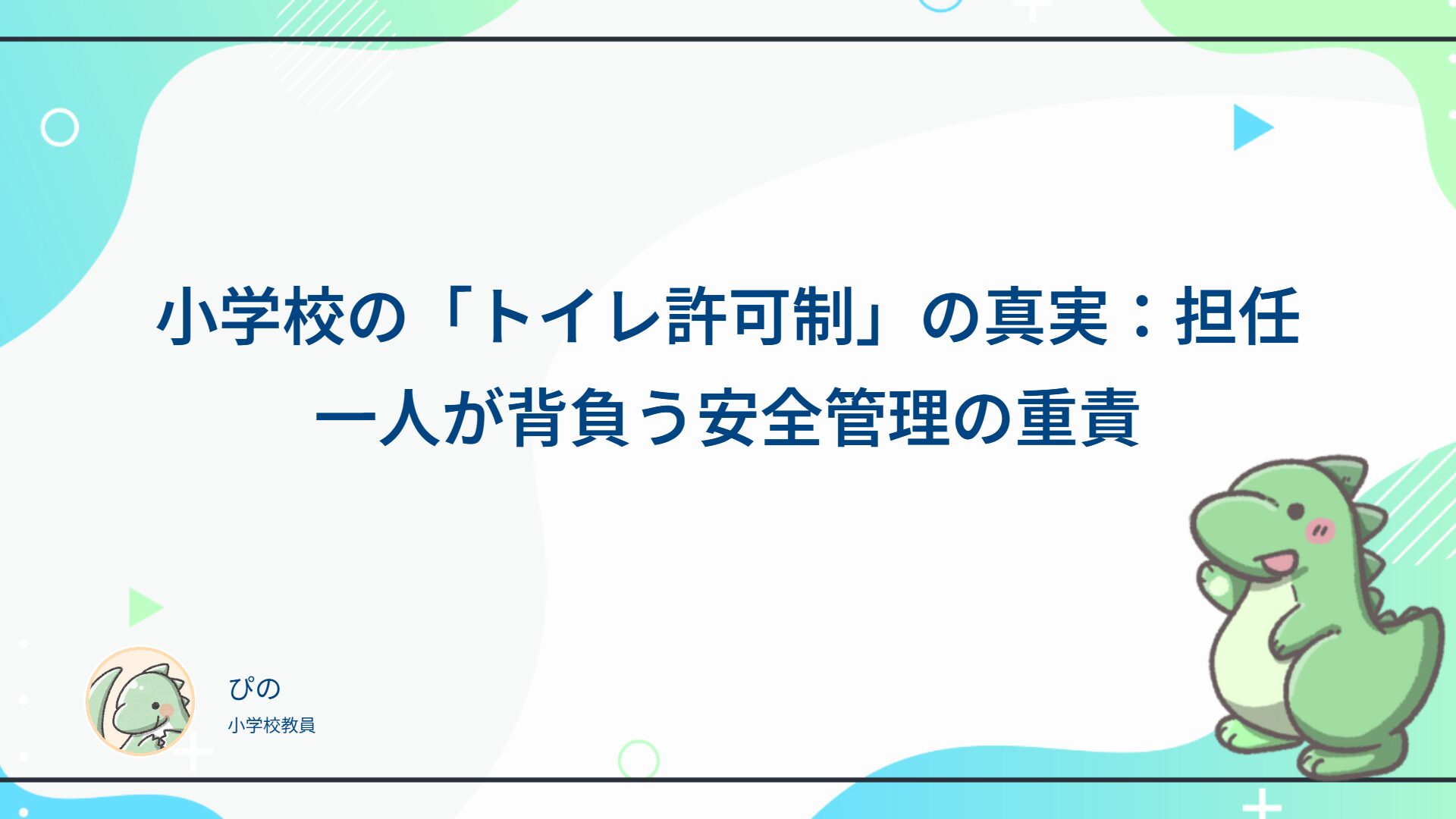
はじめに:「なぜいちいち手を挙げて言わないといけないの?」という素朴な疑問
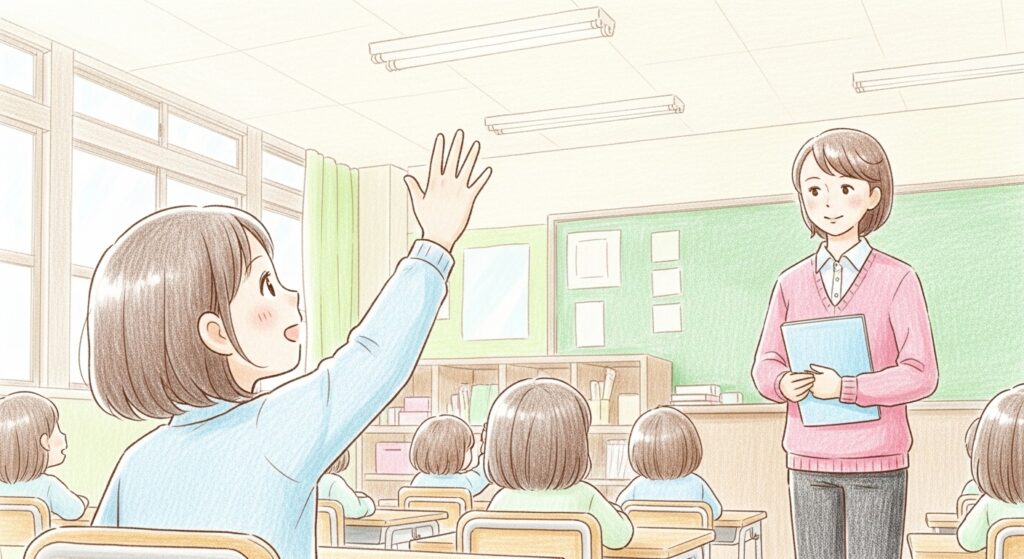
「先生、トイレに行ってきてもいいですか?」 「はい、行ってらっしゃい」
小学校でごく当たり前に交わされるこのやり取りに、疑問を感じたことはありませんか?
「なぜ子どもは、トイレに行くのにいちいち手を挙げて許可を求めなければならないのか?」
「自然な生理現象なのに、なぜ先生の許可が必要なのか?」
また、お子さんから「トイレに行きたいけど、授業中だから我慢した」「手を挙げるのが恥ずかしくて言えなかった」という話を聞いて、心配になった保護者の方もいらっしゃるでしょう。
実は、この「トイレ許可制」は、日本の小学校が抱える独特な教育環境と、そこで働く教師たちが背負う重い安全管理責任の一端を表しているのです。
今回は、この制度の背景にある現実について、詳しくご説明したいと思います。
数字で見る日本の小学校:世界有数の大規模学級と担任一人体制
国際比較で分かる日本の特殊事情
まず、日本の小学校がどのような環境にあるかを、データで確認してみましょう。
OECD(経済協力開発機構)の2024年調査によると、日本の公立学校の学級規模は小学校が27人、中学校が32人となり、OECD加盟国の中で小学校はチリに次いで2番目に大きくなっています。

この数字だけでも十分大きな差ですが、さらに重要なのは「誰が子どもたちを見守っているか」という点です。
日本の担任制 vs 海外の複数サポート体制

- アメリカ:担任教師+教師アシスタント+専門サポートスタッフ
- フィンランド:担任教師+特別支援教師+学習支援員
- イギリス:担任教師+ティーチングアシスタント+学習メンター
- 担任教師一人で平均27人の全責任を負う
- サポートスタッフは限定的(特別支援が必要な場合のみ)
- 教科指導・生活指導・安全管理すべてを一人で担当
さらに、施設面でも大きな違いがあります。
海外の多くの学校では、廊下に監視カメラが設置され、警備員が常駐しているのが一般的です。
一方、日本の小学校では、予算や文化的背景から、こうしたシステムの導入は限定的です。
法的責任の重さ:教師が背負う安全管理義務
文部科学省は学校保健安全法において、各学校における学校安全計画の策定・実施、危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成を義務付けています。
これは単なるガイドラインではありません。
もし学校内で事故が発生した場合、「安全管理を怠った」として、学校や教師に法的責任が問われる可能性があるのです。
つまり、担任教師は27人の子どもたちの「学習指導」「生活指導」に加えて、「安全管理の法的責任」まで一身に背負っているということになります。
なぜ「所在確認」が不可欠なのか
ケース1:校内での迷子・所在不明
小学校、特に1年生の入学直後によく起こる事例です。
新入生のA君が授業中に無言で席を立ち、トイレに向かったとします。しかし、まだ校舎の構造に慣れていないA君は、違う階や違う棟のトイレに行ってしまいます。そこで、自分がどこにいるかわからなくなり、教室に戻れなくなってしまいます。
担任が「A君がいない」ことに気づくのは、他の児童からの報告や、点呼の時です。この間、A君は一人で校内をさまよっている状態となります。
27人の児童がいる教室で、一人の不在にすぐ気づくことは、実は想像以上に困難です。授業に集中している他の児童たちも、最初は友達の不在に気づかないことが多いのです。
ケース2:体調急変への対応遅れ

小学生は、自分の体調変化を正確に把握し、適切に大人に伝えることが難しい年齢です。
「なんとなくお腹が痛い」程度の症状でトイレに向かった子どもが、実は急性の体調不良で、トイレで倒れてしまうということも想定されます。
もし、その子がどこに行ったかわからない状態であれば、発見と対応が大幅に遅れてしまいます。
ケース3:校外への無断外出
小学校の校舎は複雑な構造になっていることが多く、出入り口も複数あります。
「トイレに行く」と言って教室を出た子どもが、実際には校外に出てしまう可能性もゼロではありません。
特に、友達とけんかをした後や、授業でつまずいて気持ちが不安定になっている時などは、衝動的な行動を取る子どももいます。
実際に家に帰ってしまう児童も珍しくありません。
ケース4:他学年・他学級とのトラブル
校内には、1年生から6年生まで、発達段階の異なる子どもたちがいます。
廊下やトイレで、異学年の子ども同士がトラブルになることもあります。
もし、そのトラブルがエスカレートした場合、当事者がどの学級の子どもなのか、担任がすぐに把握できなければ、適切な指導や対応ができません。
総合的な安全管理の一環:トイレ許可制は氷山の一角
実は、小学校では「トイレ許可制」以外にも、様々な場面で厳格な安全管理が行われています。
体育授業での安全管理
- 準備体操の徹底確認
- 用具の安全点検
- 児童一人ひとりの体調確認
- 活動中の継続的な見守り
理科実験での安全管理
- 実験器具の事前点検
- 薬品の適切な管理
- 実験の際の注意事項説明責任
- 児童の行動把握
- 緊急時対応の準備
校外学習での安全管理
- 移動時の人数確認
- 児童全員の健康観察
- 班行動での所在把握
- 緊急連絡体制の確立
これらすべてを、基本的に担任教師一人で管理しているのが、日本の小学校の現状です。「トイレ許可制」は、こうした総合的な安全管理体制の一部なのです。
教育的意義:集団生活における責任感とマナーの育成
もちろん、安全確認以外にも生徒指導としての教育的意義があります。
「報告・連絡・相談」の基礎を身につける
「先生、トイレに行ってきます」という一言は、将来社会に出た時に必要となる「報告・連絡・相談」の基礎となります。
自分の行動を適切に周囲に伝える習慣は、職場でも、地域社会でも、家庭でも必要なコミュニケーションスキルです。
小学校時代にこの基礎を身につけることで、将来的により円滑な人間関係を築くことができます。
時間意識と計画性の育成
「休み時間にトイレを済ませる」という習慣は、時間を意識した行動計画を立てる力を育みます。
これは、中学・高校での時間割に沿った行動や、将来の職業生活での時間管理能力の基礎となります。
集団への配慮と協調性
授業中にトイレに行く際に一声かけることで、「自分の行動が集団全体にどのような影響を与えるか」を考える習慣が身につきます。
これは、民主的な社会の一員として生きていく上で不可欠な協調性の基礎となります。
まとめ:理解と信頼関係の構築に向けて
小学校の「トイレ許可制」は、決して子どもたちを管理するための堅苦しいルールではありません。
それは、日本の教育制度の特殊性(大規模学級、担任一人体制、厳格な安全管理責任)の中で、子どもたちの安全を最優先に考えた結果生まれた、必要な仕組みなのです。
教師が願うこと
教員が何より願うのは、子どもたちが安全で、楽しく、実りある学校生活を送ることです。そのために、時には「面倒だな」と感じられるようなルールも設けざるを得ない場合があります。
しかし、そのルールの背景には、常に「子どもたちの安全と成長を支えたい」という強い願いがあることを、ぜひご理解いただきたいと思います。
保護者の皆様へのお願い
お子さんが「トイレに行くのに手を挙げるのが恥ずかしい」と感じている場合は、まずは担任に相談してください。
事前に連絡をもらえば、一人ひとりの子どもに合った配慮方法を、一緒に考えてもらえるはずです。
また、「なぜこのルールがあるのか」について、お子さんと一緒に考える機会を作っていただけると、学校への理解が深まり、より良い学校生活につながると思います。
学校と家庭が手を携えて、子どもたちの健やかな成長を支えていけることを、心から願っています。